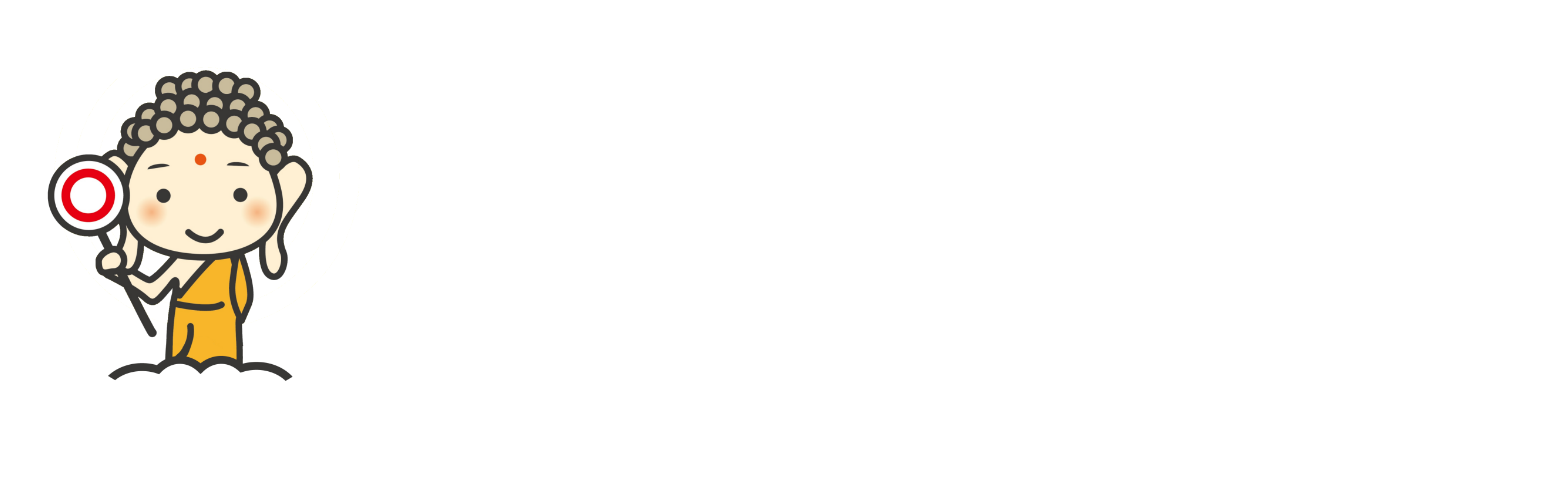このページの内容を動画で解説しています↓
以下、文による解説です。
心学研究家「小林正観さん」は言いました
頼まれごとをこなすと人生が運ばれていく
ここでいう「頼まれごと」とは
単なる「使いっ走り」 のことではありません
では正観さんの「頼まれごと」とは何なのか?
どういった仕組みで人生が変わるのか
これらを わかりやすく まとめたので
ぜひ最後まで御覧ください
小林正観さんの言う頼まれごととは
突然周りから
・あれをやってくれ
・あそこに顔を出してくれ
・あなたに会わせたい人がいるんだけど
・こういう仕事があるけど…
などの声がかかること
「あなた」だからこそ 頼まれたことであり
「あなた」への善意や好意からくる申し出のことです
※ 儲け話や詐欺は除きます
![]() お釈迦さま
お釈迦さま
具体的には
・仕事が増えたり
・お金に困らなくなったり
・魅力的な仲間が増えたり
・人生が楽しくなったり
・自分では想像できないステージに運んでもらえたり
![]() お釈迦さま
お釈迦さま
「頼まれごとが来たら断らないほうがいいですよ」とのこと
頼まれ事を断らなかった武豊さん
日本競馬界のレジェンドと言われる
通算4000勝を超える JRA歴代最多勝 記録を持っています
武さんは どんなに無名の馬であっても
頼まれて 日程が空いてたら、馬や状況を選ばないで 全部乗ったそうです
頼まれごとを断らないでいると
お金・仕事・仲間が増えて
人生が楽しくなるようです
人生は頼まれごとだけでいい
私たちは 生きていくうえで
「夢を持て 目標を達成しろ 」と教わりました
もちろん その生き方も素敵ですが
「頼まれ事・やるはめになったこと」をこなすだけの人生も楽しいと 正観さんは 言います
なぜなら、頼まれごと こなすと
相手から喜ばれるから
人間は「喜ばれたら嬉しい」という本能があるので
人生が楽しくなる
人間は1人では生きていけません
人の間で生きて初めて人間
ですからお互いに助け合うこと、頼み合うこと、頼まれること、してあげ合うことが
この世に生まれてきた目的の一つでもある
頼まれるのは大変
誰でも 頼まれごとが来るわけではありません
「頼まれごと」が来るには条件があります
一つは 日々
五戒とは「不平不満・愚痴・泣き言・悪口・文句」の5つ
五戒を言わなくなって 3ヶ月~6ヶ月すると
頼まれごとが始まるらしいです(人によっては6ヶ月以上)
もう一つの条件は 頼まれやすい人柄であること
眉間にシワをよせて
いつも怒っている人に頼まれごとはやってこない
能力が高くても人柄がよくなければ頼まれない
「頼まれやすい」人は 人柄のよい人 であるようです
頼まれごとを 断るのは傲慢
ある時 正観さんが
とある女性の字を見てこう言いました
「字がとてもキレイですね
今後 字を書いてほしいと頼まれたら
引き受けたほうがいいですよ」
女性は「実際、字を書いてほしいと頼まれることが多いのですが、まだまだ下手なのでお断りしています」
正観さんは言います
何かを頼まれた時「私には力がないので とてもできません」というのを
せっかく頼んで下さったにもかかわらず断るのは、
本人の「思い込み」や「奢り」が ただ強いだけ
手か上手いかなんて 本人が決めることではなく
「自分で決めている」ことが傲慢
頼まれ事は、まったく無理な内容なら 断っていいが
引き受けられそうなら 引き受ける
しかし、気合を入れないで
適当に いい加減にやるのがおすすめ
適当とは あなたにとって適度にちょうどよく
いい加減とは、ちょうど良い加減
今持っている力で頼まれたのだから
今の力でやればいい
今以上のことを要求されているのではない
だから 頼まれた時点のレベルで
できる範囲でやればいい
気負いすぎるのは、ある種の価値観に縛られているから
(もっといえば「よく見せよう」と思ってしまうからこそ)
引き受けたからにはいい仕事をしなくては
完璧にこなさなければ と思うから苦しくなる
実力以上に頑張るのもいいですが
適当に 良い加減で ニコニコと
頼まれ事をやっていくほうが面白い
人生は、目標を達成するためではなく
いかに喜ばれる存在になるか(頼まれ事をこなすか)に尽きるそうです
頼まれごとに優先順位はない
頼まれ事は 無料も来るけど、有料で来ることもある
有料で頼まれた際、
「お金はいただけません」というのは傲慢
理由は、お金は宇宙のも(みんなもの)であり、
「自分のお金」と思っていることが傲慢
お金は 人から人へ通過させるだけでよい
また、頼まれ事に優先順位もない
たとえば、先に無料の頼まれ事を引き受けたが、
後日、有料の頼まれ事が被ってしまっても、
先約を優先する
ものごとに「重要」「重要でない」という区別はい
もし 先にきた頼まれごとを
「こっちのほうが条件がいい…」と
キャンセルして変更するのを繰り返すと不誠実となり、
必ずそれなりの人生を歩むことになる
不誠実を続けて行けば、「この人はキャンセルが多い」と
次第にその人への頼まれごと(仕事)は減っていく
先に引き受けたものを誠実にやっていくことで、
次第に 有料で頼まれることが多くなり、
その人を支援する方向で人生が変わっていく
断っていい頼まれごと
頼まれごとの中には、断っていいもの(そもそも頼まれごとに含まれないもの)がこちら
・お金貸してという頼み
・人数合わせの頼み
・先約が入っていたとき
・儲け話や 詐欺
・物理的に無理なこと
(100kgを持ち上げてとか)
・能力的にできないこと
(例えば英語を話したことがないのに英語の先生をして)
・自己嫌悪が生じる頼まれごと
(引き受けたら自己嫌悪が生じる内容は断っていい)
![]() お釈迦さま
お釈迦さま
もし断ってしまったら…
正観さんは 頼まれごとは
なるべく断らないほうがいいと言いましたが
断っても大丈夫
正観さんが言ったのは方程式であって
規則ではありません
それに、「頼まれごと」は断っても
五戒を言わずにいると またやってくるので
深く考えなくてもいいでしょう
よく「ピンチはチャンス」と言いますが
それと同様に「頼まれごとはチャンス」と捉えたらいい
それらを踏まえて 「断る・断らない」を
自分で選択されたらよろしいかと思います
使命に気づく
頼まれごとが始まったら
ただ ひたすらやってみる
そうすると、ある方向に進んでいることに気づく
「これをやるために生まれてきたのかな」と
自分の使命・役割に気づくことがあるようです
使われる命 と書いて 使命
その方向で使われることが
生まれる前 自分で書いてきたシナリオ
頼まれごとは相手を喜ばせるますから
楽しい人生になる
自分で達成目標を作って 必死になっても
誰も喜んでくれないのかもしれない
頼まれ事は、頼んだ人は必ず喜んでくれている
正観さんは言います
人間がこの世に生まれた理由の一つに
「人格を磨く」ためがある
人格を磨くのは 経済的に成功するとか
社会的地位(名誉)を得るのではなく
いかに自分の存在が 人から喜ばれるか(頼まれごとをこなすか)
それこそが魂の目標の一つでもあるようです
後世に残る仕事は頼まれごと
中世ヨーロッパの時代
宮廷音楽家たちが活躍しました
宮廷音楽家とは、宮廷に雇われていた作曲家・演奏家
代表格にはベートーヴェン・モーツァルト・シューベルト・ショパンなど
宮廷音楽家たちが、王族から頼まれて作った音楽と
自分の意思(好み)で作った音楽 と
どちらが今も 残っているか…
答えは9対1 で頼まれて作った音楽
同様に宮廷画家 のミケランジェロ・レオナルド ダ ヴィンチ・ルーデンス・ヴァン ダイクたちの絵も9対1 で王族から頼まれて描いたものが残っているそうです
頼まれ事が生きる目的
頼まれごとをこなして 喜ばれる人生は楽しいそうです
正観さんいわく 人間の生きる目的とは
必死に何かを成し遂げることではない
長く生きることでもない
努力することではない
努力するなと言っているのではなく
努力が好きならそれで構わない
でももう一つの生き方がある
頼まれ事をただひたすらやって人生を終える生き方
生きている間に どう喜ばれるか
その喜ばれる一つのことに
「頼まれごとを淡々とこなす」というものがあります
人によっては「頼まれごと」で始めたことが
そのまま仕事になる人もいるようです
結婚は頼まれ事なのか?
本人が頼まれたと思ったら頼まれたごと
これは頼まれごとではないと思えば違うとのことでした。
最後に
基本的に「自分ができない頼まれごと」は来ないようになっているらしい
ですからもし、頼まれごとが来たら 気負わずに、
できそうなものは 引き受けてみたらいかがでしょうか
きっと人生が楽しい方向へ運ばれていくと思います
ちなみに頼まれごとは 今まで五戒を言ってきた数だけ遅れるらしいです
五戒を5千回言ってきた人は 5ヶ月遅れ
1万回言ってきた人は10ヶ月遅れるらしい
ですから、頼まれごとが来てほしいと思う人は
五戒を言わないことから始めてみて下さい
今回のお話が参考になりましたら幸いです
参考にさせて頂いた書籍↓
魅力的な人々