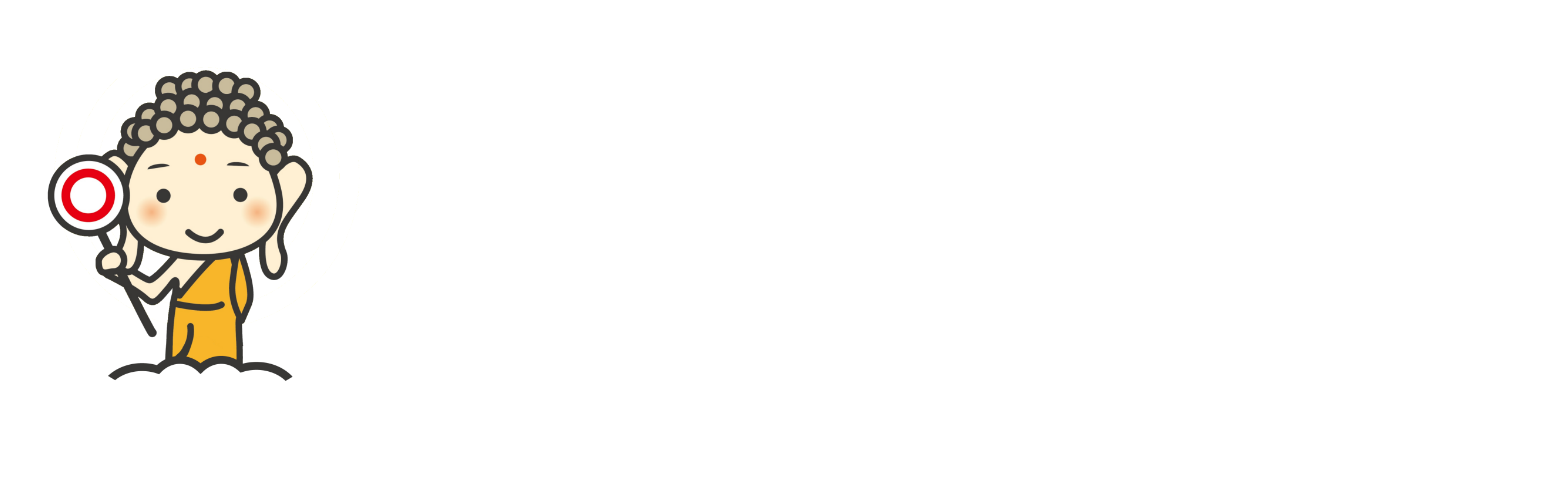このページの内容を動画で解説しています↓
以下、文による解説です。
つい子育てにイライラしていまい
疲れ果てる親も 多いのではないでしょうか
この動画では、教育学博士でもあった小林正観さんの話をもとに
子育てにイライラしなくなるポイントをまとめました
ぜひ最後まで ご覧ください
叱らずに 工夫してみる
子どもを叱って、命令したとしても
言うことを 聞かないこともあります
そんな時は、工夫をこらし
「楽しさとセット」にするといいようです
![]() お釈迦さま
お釈迦さま
医師でもあった漫画家「手塚治虫さん」が
子どもの頃 風邪を引きました
当時「エキホス」という風邪薬があり
喉に塗るのだそうですが
手塚さんはこの薬の匂いが苦手で
とても嫌がったそうです
そんな手塚さんに対してお母様は
「薬なんだから ちゃんとつけなさい」と叱ったりはしませんでした
なんと「エキホス」の創作話を 聞かせてあげたそうです
「昔 昔 ある小さな村の薬屋さんに エキホスが売られていました」
このように エキホスを主人公とした物語を聞かせたのです
そして物語の締めくくりとして
このエキホスをつけると
つらい風邪も治ってしまうのよ と言った
母親から「エキホス物語」を聞いた手塚さんは
「つけてみよう」という気になったとのこと
![]() お釈迦さま
お釈迦さま
私たちの日常生活においても
「早く用意をしなさい」
「いつも言ってるでしょう」
ついそうやって
子どもを叱ってしまう大人が 多いのではないでしょうか
大人の言い分としては
「叱らないと やらないから」
「何度でも同じことを言わせるから」と言いたくなりますが
「叱らないとやらない」というのは
大人の思い込みかもしれない
子供の側にも「やらない理由」(やれない理由)がある
そこをまず考慮したり、
解決すれば
案外 やれるようになるもの
そういう工夫もしないで
子どもを ただ叱りつけるのは
大人の怠慢かもしれない
親であるあなただって
姑から 頭ごなしに注意されたり
命令されたら
いい気分がしないでしょう
子どもだってきっと同じです
ですから もし
子どもを毎日叱るのに疲れた…
と思っているなら
そのワンパターンから抜け出すためにも
なにか工夫してみると楽しいし
子どもがやる気になってくれるかもしれません
たとえば、子どもが片付けをしない場合は、
片付けをゲームとしてやるといいようです。
お母さんとどっちが早く片付けられるか遊ぼうという具合に
子どもは繰り返す
親がついイラッときてしまう理由に
「子どもが何回も繰り返すから」という状況 があります
「何度言ったらわかるの」
「この前約束したでしょ」
このような言葉を言ってしまいますね
![]() お釈迦さま
お釈迦さま
子どもは何回でも 同じことを繰り返すもの
それが子どもの特徴なんです
繰り返しながら
少しずつ できるようになっていくのです
それが当たり前なんだと
始めから頭に入れておけば
イライラすることも少なくなるでしょう
つまり、怒らずに
何回でも 伝え続けること
怒ることは疲れますが
ただ伝えるだけでいいのなら
そのほうが 親も子も
らくで楽しのではないか
子どもの間違った行動に対して
親から見て子どもは 困った行動をとることがあります
しかし、子どもにも 理由や 事情があることがある
そこを考えないで
大人の価値観で叱ってしまうと
信頼関係を傷つけたり、子どもの興味を潰すこともある
たとえばこんなお話があります
飛行機を発明したライト兄弟の弟
オーヴィルは
幼稚園をズル休みしていました
オーヴィルは「行ってきます」と家を出た後に
幼稚園には行かず
友達の家に行っていました
友達の家には「壊れたミシン」があり
それを直したくて 行ったそうです
事情を聞いた母親は
叱ったりはしませんでした
一体 なぜか…
それは、ズル休みの理由が
好奇心からくるものだったから
つまり「なぜ さぼったのか」をしっかり見ていた
もし、ここで母親が 叱っていたら
オーヴィルの関心を奪い、飛行機はできなかったのかもしれない
だからといって
親として サボりを許容することはできないという人も多いでしょう
![]() お釈迦さま
お釈迦さま
「順番」が大切
まず最初に子どもの言い分を聞く
そして子どもの気持ちを理解することが先
親の気持ちを伝えるのはその後なんです
「そういう理由だったの。
それでミシンは治ったの?
どんなふうに試したの?」
こうやって 聞いてあげたら
子どもは いきいきと話してくれるでしょう
そうやって まず子どもの気持ちを受け止めた あとで
親の伝えたいことを伝えるという順番がいいみたい
さらに 子ども というのは
頭ごなしに怒る人の言うことは聞かないようです
逆に 「自分の気持や事情を聞いて
受け止めてくれた人」の言うことなら聞く耳を持つようです
ですからみなさんも 「順番」を大切にしてみてはいかがでしょうか
本音を伝える
子育てにおいて
叱るのではなく「本音を伝える」ことも大切だと正観さんは言います
![]() お釈迦さま
お釈迦さま
江戸時代の教育者で知られる
吉田
獄中に絶食したことがあります
理由は「自分がしてきた行動(罪)」に対して
「命をかけて問う」 という決意から 絶食を始めたのです
この状況を聞いた父親は
松陰に手紙を送りました
内容は「バカなことをするな」という叱責でした
この手紙を読んで
松蔭は絶食をやめませんでした
次に母親も手紙を出しました
母親は「あなたのことが心配です あなたに生きて欲しい」という内容を書いた
この手紙で 松蔭は 絶食をやめたそうです
正観さんは言います
叱ったり 責めたりするのではなく
本音を伝えることは
子育てにおいて重要です
厳しく叱責された子どもが、
叱られた意味を納得して
行動するのはそうそうない
たいていは、仕方なく言われた通りにするか
あるいは反発心が生じる
さらに 幼い頃から、それが繰り返されると
自分自身で 考えて行動できる子に育ちにくくなる
しかし、松蔭の母親のように
「あなたにそうしてほしいと思う本音」を
穏やかな口調で伝えると
子どもはそれをキャッチできる力が備わっているとのこと
そうやって 本音で伝えられたら
相手の気持の意味を考え
子どもなりに 次からどうしていこうかと考え始めるとのこと
親は つい 「親の理想どおり」に育ってほしいから
あれや これやと説教しがちですが
親の思いどおりにしようとすればするほど
子どもが自分で考える力を奪ってしまうのかもしれません
なので頭ごなしに叱らずに
本音で話してみてはいかがでしょうか
自分で考える力を養わせることが
親の本来の役目ではな ないでしょうか
子どもの才能を奪う
生まれたばかりの象の首にひもをつけ
杭に繋いでおく
引っ張っても抜けず、何十日かたち、杭が抜けないことを悟った象の子は、それ以降紐を引っ張らなくなる
大人になっても、引っ張らず
紐を外しても逃げないのだとか
のみをつかまえてコップに入れて手で塞ぐ
飲みは何十回と飛び跳ねるが
あるときにピタリとやめる
手をどけても飛ぶことはやめて
そのままコップのそこでじっとして死んでしまう
![]() お釈迦さま
お釈迦さま
幼い頃に
ダメ・いけない・ちゃんとしなさい・もっともっとと言い続けられたら
力が足りない・能力が低い・今のままじゃいけないと言われ続けたらのみになる
子育ては弓矢
子育ては弓矢に似ている
ほんの少し引いたら、弓矢もほんの少ししか飛ばない
十分引いたら弓は思い切り飛ぶ
また手を離さないと矢は飛んでいかない
弓矢を引く期間が、子どもが飛び立つ準備をする期間
その期間に親が子どもにしてあげられることは、子どもに十分な愛情を注ぎ、うんと大切にし育てること
手放した後に、「あれもやってあげればよかった」と後悔しなくていいように
そして矢を放つ時が来たら、いつまでも握らずに思い切り手放す。
すると子どもは自分の力で飛び立っていく
最後に
いかがでしょうか
ついつい 親の価値観で
子どもイライラすることもありますが
見方を広げていくと
イライラする機会は減るのではないですか
あの電気を発明したエジソンだって
クラスの成績はビリで、小学校をも中退しています
ですが信じ続けてくれた母親の愛があったからこそ
好きなことに熱中し 才能を伸ばした
![]() お釈迦さま
お釈迦さま
すべての子どもに素晴らしい才能が備わっている
そしてその才能の芽を摘まずに伸ばし続けていけば
仕事(お金)には困らなくなるようなのです
愛情たっぷり 注いだ子どもは
大人になってから人間関係もうまくやっていきます
ですから 親の思いどおりにしすぎるのはやめましょう
親の思いどおりにしようとしなくなれば
イライラも減るはずです
ぜひ 見方を広げて 子育てを楽しみ
人生も ラクに楽しく過ごされてみては いかがでしょうか
参考にさせていただいた書籍↓