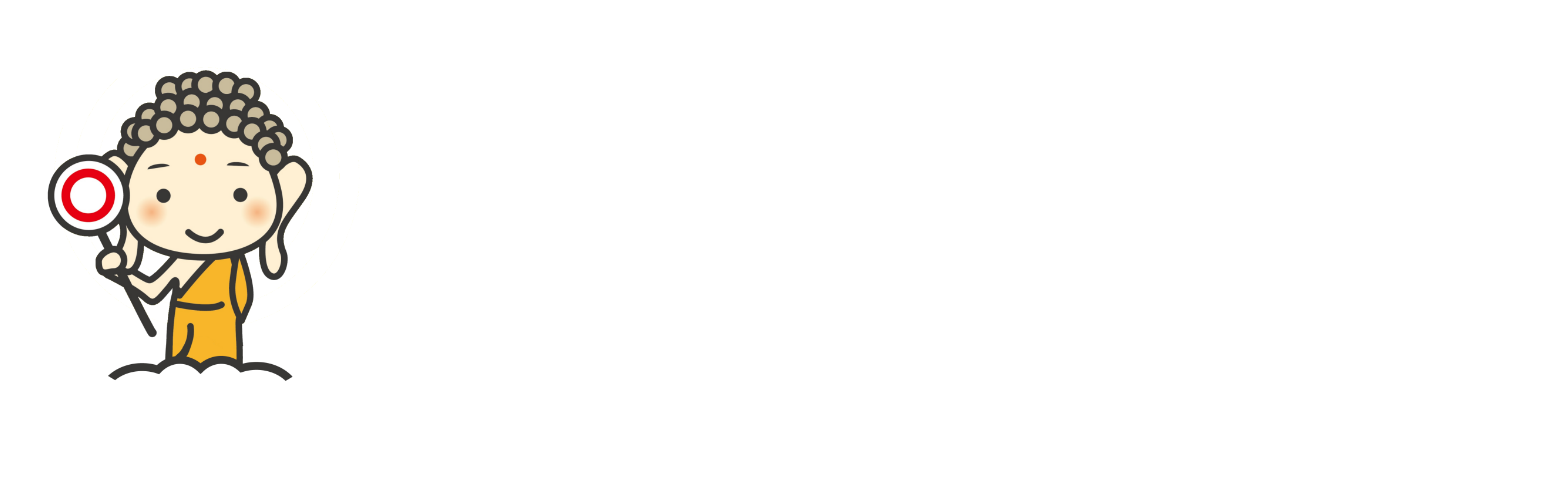小林正観さんの講演は、2時間のほとんどがダジャレ…
なんて聞いたことがある人も多いかもしれません。
それは事実だと思います。
ただ、その時によって ダジャレの多さも変化してくると思いますが、
でもなぜ正観さんはダジャレを多めにしていたのか?
その理由をまとめてみました。
心学研究家「小林正観さん」は
年間 330回もの講演をこなしていた
2年先まで予約が埋まっていたとか
とても多忙に思えますが
正観さんは 全然疲れなかったと言う
では どんな思いで
講演をこなしていたのでしょうか…
ある秘密が隠されていました
そこを紐解いていくと
私たちが
ラクに生きるヒントが隠されていますので
ぜひ参考にしてみてください
正観さんの講演会は
ほとんどダジャレだったと言います
一体 なぜか?
それは 正観さん自身が
楽しんで 幸せに感じているということが
会場の人に自然に伝わればいいと思っていたから
固い話だけでは 楽しい講演にはならないでしょう
正観さんいわく、
楽しくて 幸せな気持ちが伝わるなら
本当は何も話さなくていい
でも 間がもたないから話している
なにかすごいことや
大切なことを伝える必要はない
ただ笑ってもらえればいい
もっと言えば 私自身が笑われていればいい とのこと
正観さんの言う「実践」に
「笑い」がありますが
笑うことで、体がリラックスしたり
心の突っかかりがとれて
元気になってくれたらそれでいい
悩みを抱えている人が、
くすっと笑うことができたのなら
その人の心が変わるかもしれない
違う生き方に気づけるかもしれない
そういった思いも含め
笑いを重視されていたのではないでしょうか
人間は近くにいる人の共振共鳴を受けます
会場の9割が笑っていたら
「悩みを抱えた人」でも、
その周波数を受け 高い波動で帰る
実際に、最初はぜんぜん笑わなかった人が
回数を重ねる内に
笑顔の素敵な人に変わっていった
悩みがなくなった
ということがよくあったそうです
正観さんは自分の講演が始まる前
会場の後ろに座っていることがありました
SNSがない時代
正観さんの顔は 広くは知られておらず
そこへ 初参加の人が隣に座り
よく こんな風に話しかけられたそうです
「正観さんという方を全然 知らないのですが
いい話だと聞いて 参加しました
どんな方なんでしょうね?」
「私は聞いたことがありますが
全然 大した話ではありません
ほとんどダジャレ です」
「でも いい話だと聞いてきたのですが…」
「大したものではないですから
期待しないほうがいいですよ」
「そうですか」
開始時刻となり
司会の方が言います
「それでは正観さん お願いします」
「はい」と答えて
立ち上がった正観さんを見て
隣の人はとても驚いた
こんな光景が何度かあったそうです
「自分が講師の先生に見えないうちは
講演を続けてもいいかなと思っています
でも 誰がどう見ても
「講師の先生が入ってきた」と
背筋を正すようになったら
講演をやめようと思っています
このように言われていました
人は 周りから「すごい」と言われると
自己顕示欲がわいてきます
「もっと評価されたい」
「すごい人と思われたい」
ですがこの欲を持ってしまうと
それが悩み・苦しみの原因となる
人前で喋るのが 緊張したり
手応えがなかった時に「落ち込む」原因となる
人間ですから
100%うまく行き続けることなんてありません
最初から「自分は大したものではない」
と思い切ることができたら
自分がラクに生きられるのです
正観さんは ご自身のことを
日本で一番 使命感がない講演家 です
と言われてました
意外に思われるかもしれませんが
正観さんは「世の中をよくしよう
人を変えてあげよう」とは
全く思っていなかった
ただ、正観さん自身が
明るく 楽しく生きて
その方法を伝えるだけ
正観さんいわく
使命感は持たないほうがいい
もし使命感を持ってしまうと
相手が変わらなかった時に
それが、「怒り」となったり
もしくは 自分が悩む原因となるから
だから 使命感は持たずに
ただ 「こんな方法がありますよ」と「伝える」だけ
自分に使命を感じるのはいいのですが
人に強要する(使命感)のはよくないとのこと
強要がはじまると
口から出る言葉は楽しいものではなくなりますね
ですから、正観さんは
自分がどう生きるかだけで
淡々と話をされていたのではないでしょうか
もちろん
世の中が明るくなっていけば嬉しいし
人が明るく変わっていけば嬉しいことに変わりない
ただ、「自分が変えなくては」という使命感は全く持っていなかったとのこと
正観さんの講演会を
最も多く主催したと言われる人が
高島亮さん
後の正観塾「師範代」となる方です
そんな高島亮さんは、
正観さんの講演について こう語っています
正観さんの講演は100人を超える時もあり
リピーターも多かった
主催者の身としては
リピーターはありがたい存在
毎回 新しい話を用意して
ぜひリピーターを楽しませてほしい
しかし、正観さんは毎回 必ず
「今日はじめて来た方は?」と聞いて
自己紹介から始める
主催者からすれば
いつも同じ話をしていたら
飽きられてしまって
大事なリピーターさんが来なくなってしまう
しかし正観さんは言いました
「飽きられてもいいんです」
「私の基準は常に
一番弱い立場にある人
講演会であれば
初参加の人を基準にする
だから毎回 自己紹介からはじめます
その結果、
リピーターが来なくなっても構いません」
と言われたそうです
最初から「飽きられてもいい」
「高い評価を受けなくてもいい」
と思っていたら
悩み・苦しみもないのです
そして、弱い立場に目を向ける
親子関係なら子ども
上司と部下なら部下
弱い立場を考えることも
人間関係をスムーズにさせる
重要なコツではないでしょうか
正観さんはこう言いました
「好きで講演をやっているわけではありません
「いやで やっているのでもありません
頼まれたから やっているだけです
正観さんいわく
人生は 笑顔で 淡々と生きるだけいいらしい
私たちは 今の仕事に不満を言ったり
将来に不安を感じたりします
ですが どんな仕事も
必ず 人の役に立っている
必ず 人から喜ばれている
ですから、自分の感情で
「楽しくない」「つらい」という
ネガティブな感情を挟むのではなく
頼まれたから(やるはめになったから)と
淡々とやるだけでいいそうです
どんな仕事であっても、
自分にご縁のある人と出会い
自分にご縁のある仕事であることに変わりはない
ですから文句を言わず
笑顔で淡々と生きるだけでいいそうです
そして そのような人には
お金の問題も含め 人生がスムーズに行くようです
結局 人生は、
自分で「ああしたい」「こうしたい」という思い
「ああじゃなきゃダメ」「こうでなきゃダメ」という思いが
重くのしかかっている
まさに正観さんの言われた
「思い」が「重い」
「思い」を減らして
人生 おまかせで生きてけば
足取りも軽く
心も軽く生きられるのではないでしょうか
正観さんはこうも言いました
人生を真剣に生きるのはいいですが
深刻に生きるのはやめましょう
人生は笑い飛ばして生きるといいですよ
今回のお話が参考になりましたら幸いです
参考にさせていただいた書籍↓